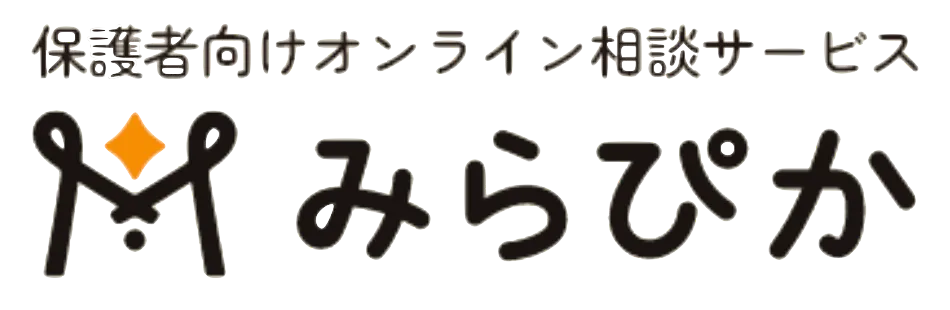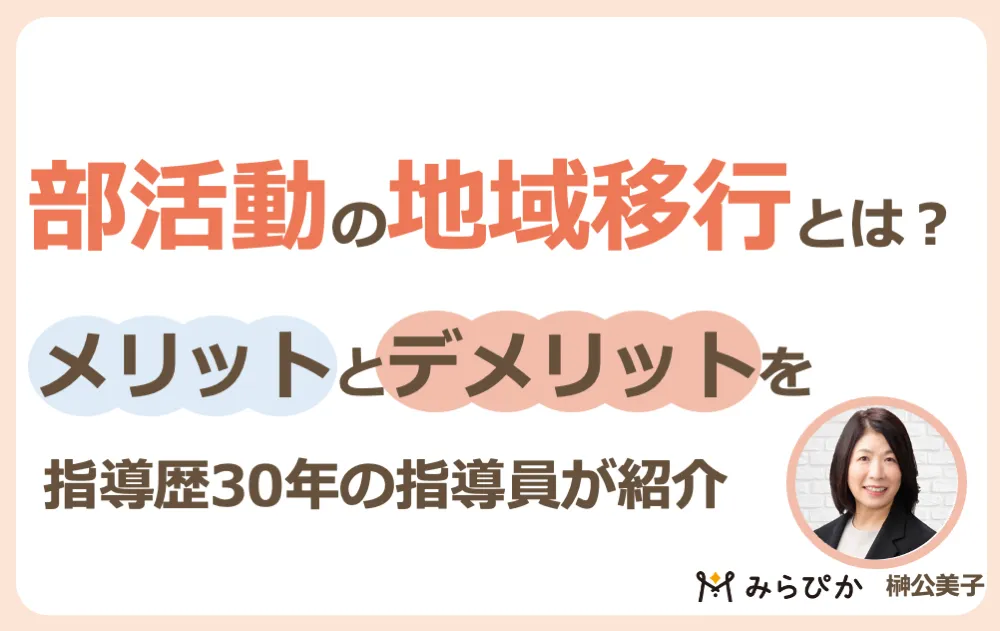
はじめに
最近では、部活動の地域移行の取り組みが進んでいます。親としては子どもへどんな影響があるのか、どんなメリット・デメリットがあるのか、知っておきたいところではないでしょうか。地域移行することによって、親のときの部活動とどう変わっていくの?とこれまで経験をしたことがないので気になっている方もいるかもしれません。
部活動の地域移行は子どもには選択や交流が広がるといったメリットがある一方で、家庭への負担や組織運営、競技力向上に伴う課題といったデメリットも考えられます。30年以上、スポーツ界、特に現場で教員、コーチ、大会運営などに携わってきた指導者から見た部活動の地域移行についての詳細や現状をお伝えしたいと思います。
部活動の地域移行の背景と目的
まずはじめに、部活動運営が年々難しくなっている現状についてお伝えします。
一つは、近年の少子化の影響です。生徒数の減少に伴いこれまでと同様の運営体制では維持が難しくなり、中学校、特に公立校では、部員の減少や部の存続の危機に見舞われています。
もう一つは、教員の働き方改革の影響です。中学校の教員の業務は、通常の授業に加え、クラス運営や生徒指導、会議など多岐に渡ります。本来の業務に加えて部活動に関わると、放課後の活動指導、休日練習や大会帯同など、おのずと長時間労働になってしまいます。そのため、教員の就業時間、心身への負担、休養時間不足などが、働き方改革により問題視されるようになりました。
その現状を受け、学校現場だけでは解決が難しくなった部活動の課題に対して、スポーツ庁や文化庁から部活動のあり方についてのガイドラインが出され部活動改革が推進されるようになりました。
スポーツ庁及び文化庁では、2018年度に策定した二つのガイドライン「運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン」及び「文化部活動のあり方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で、新たに「学校部活動及び新たな地域クラブ活動のあり方等に関する総合的なガイドライン」を策定しました。
このガイドラインには、学校部活動の地域移行への環境整備が提唱されています。
これは、2023年度から「改革推進期間」として、外部の部活動指導員が部活指導を行うことや、部活動を地域で活動する民間のクラブや教室に連携や移行させるなどの取り組みを、各地域で段階的に行っていくことを提示しています。
このようなことから今後は、行政や学校の方針により、部活動のあり方が徐々に変わっていくことが予想されます。
部活動改革は始まったばかりで、各所からの今後の報告にも注目したいところではありますが、地域移行のメリットとデメリットをまとめてみました。
地域移行のメリット
部活動の選択の幅が広がる
現在は少子化の影響などで、通っている学校の部数や部員数が少ない、廃部になるといった諸問題が起きています。部活動の地域移行により、高校やクラブチームといった地域のリソースを利用し、やりたいと思うスポーツ活動や文化活動を選択して行うことが可能になります。選択肢が限られていた子どもも、やりたいことを追求する機会を得られます。
地域人材との交流
部活動の地域移行に伴い、他の学校の子どもとの交流や、地域の指導者といった学校の枠を超えた地域での交流を経験できます。これは、子どもの視野を広げ、多様な経験を積むことにもつながります。
また、地域の施設を利用することができることでより充実した活動が可能となり、子どもたちの成長が促進されます。
専門的な指導
部活動の地域移行によって、学校外の専門家が参加することで、子どもは高度な技術や知識を学ぶ機会を得る可能性が広がります。また、これは、子どもの健康状況などへの細やかな対応などがなされ、行きすぎた指導、閉鎖的な環境でのハラスメントなどが減ることも期待できます。
さらに、教員の負担軽減にもつながり、教育の質の向上にもつながっていくでしょう。
地域移行のデメリット
一方で、部活動の地域移行には検証が必要な課題も存在します。
お金と時間の増加
部活動の地域移行には、コストと時間の増加が伴います。参加料や指導料、移動に関わる交通費が新たに必要になる場合があります。また、活動場所への移動や保護者の送迎にかかる時間も増えることもあります。これらのコスト増加と時間の負担は、家庭にとって部活動を行うか、重要な検討事項になりえますし、参加が難しくなる可能性があります。
コストや時間の増加は悩ましいところではありますが、それを上回る成果や経験が得られるのであれば、その提供する価値と効果は大きなものになると思います。
組織運営の難しさ
部活動の地域移行は、現在各地域で土台を作っている過程なので、運営状況が定まっていない場合も予測されます。新しい体制下での運営責任者の選定、適切な指導者の確保、そして十分な予算の計画と管理は、各地域の具体的な状況に応じて慎重に対応する必要があります。
これらの課題に加え、地域コミュニティ、保護者との協調やコミュニケーションも重要です。問題が発生した際に、ひとつひとつ解決しながら活動を発展させることが、将来の子ども達の環境づくりの鍵になります。
技術力・競技力向上の悩み
部活動が地域移行することで、一般のクラブチームや文化教室的な発展をすることにより、子どもたちの競技力、技術力の向上がより求められることが予想されます。また、大会への出場、作品の出展など多くの機会を与えられることで、その期待に応えるためストレスを感じる恐れもあります。
行き過ぎた指導や活動は問題がありますが、ひとりひとりが自分の課題に向き合い乗り越えることで、子どもたちの成長につながるでしょう。
部活動の地域移行の事例
改革推進により、各地域では試験的に運動部活動を推進する事業が行われるようになりました。
スポーツ庁のホームページでは、「部活動改革ポータルサイト」にて全国の取組事例が紹介されています。
私の住む大阪府では、大阪市、守口市、泉大津市(令和3年・4年度)、大阪狭山市、島本町(令和3年度)、箕面市(令和4年度)における事例が紹介されています。
例えば泉大津市の取り組みは、合同部活動推進事業ですが、市と大学の連携により、学校部活動種目は指導者派遣と3中学校合同部活動で、学校部活動以外の種目は、合同ゆる部活動やレクリエーションスポーツ教室体験などで成果報告をしています。また、タブレット端末を利用した部活動トレーニングのICT化やグッドコーチ養成セミナーで学んだ人材を派遣することなども報告されています。
その結果、生徒の自主性向上、異年齢交流、専門的指導の機会創出などが効果として現れているようです。
毎年事業を検証して実施、報告することで、地域や学校現場からの理解も得られつつあります。
私自身は、競技団体で勤務している時に指導者養成や指導者派遣業務にも携わりましたが、指導者と学校現場のマッチングについては、技術指導以外にも考慮しなければならない事項があり、責任が重いと感じていました。その点、泉大津市のように、指導者養成について大学と連携することで、一定の基準をクリアした学生や指導者が派遣されるのであれば学校や保護者も安心できると感じました。
部活動の地域移行が進む中で保護者ができること
皆さんのお子さまは、部活動に対してはどのように考えているでしょうか?保護者側の気持ちとしては、お子さまの希望にそった活動をしてほしいと思われることでしょう。
そのためには、まず、お子さまが進学に際して取り組んでみたいことや興味を持っていることの話に耳を傾けていただきたいと思います。
進学前であれば、一緒に入学予定の学校のホームページを閲覧したり、その学校に通っている先輩や保護者から学内外の情報収集をするのも良いかと思います。
また、私立校など学校によっては、部活動に力を入れていることを特色として、積極的に生徒募集を行っている場合もあります。
幼少の頃から、お子さまが取り組んできたスポーツやお稽古事などを部活動で継続したい場合は、学校のオープンスクールに参加して、実際の活動を見学した後に受験の検討をするのも良いでしょう。
まとめ
部活動の地域移行は、多面的な影響を持つ複雑なテーマです。子どもたちに新たな交流の場と多様な体験を提供する一方で、組織運営の難しさや家庭への経済的・時間的負担の増大といった課題をもたらします。
しかし、選択肢が増えたことで子どもたちの自己決定能力を養う絶好の機会となることは間違いないでしょう。
子どもたちには、その年代でしか経験できないことがあり、部活動での経験を通じて子どもたちは成長していきます。
各地域では、地域特性に合わせた新しい事業がブラッシュアップされています。新しい情報もスポーツ庁や都道府県、市町村のホームページなどで報告もされていますので、ぜひチェックしてみて下さい。
アンケートが実施されている地域もありますので、お子さまや保護者さまの声を直接届けることができるかもしれません。子どもたちの環境を私たちの声で創造できるチャンスだと思うとワクワクしますね。
よければみなさんの素朴な疑問やお困りごとがあれば気軽に話してみてください。
お試しで30分からお話しいただくことができます。
以下のLINEに友だち登録いただき、オンライン相談についてチャットをいただければ、時間の調整もすぐにできますので気軽にご連絡ください。

榊 公美子
みらぴか認定サポーター
中学、高校、大学、クラブチーム、シニアチームとバスケットボール選手として活動。
体育教師、クラブチームコーチと指導する側から競技団体(バスケットボール協会)で大会運営や指導者養成など多岐に渡る職業を経験。現在は、バスケットボールの普及活動やアスリートのサポート事業などを行う。育成年代の選手達が、スポーツでの経験を通じて成長し、大人になってもスポーツの良さを次の世代に伝えていくことができる環境づくりを目指している。
お子さまの部活動についてお悩みの方は榊さんに相談してみませんか?